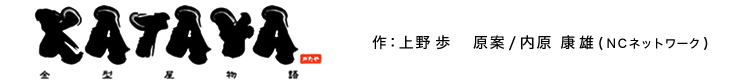

明希子は誠一を実家のセダンの助手席に乗せて走らせていた。
力のない表情で誠一が窓外の風景を眺めている。
退院した日、久し振りに自動車に乗って帰宅する時、タクシーはそれほどスピードは出していないのに、誠一の眼には、景色がものすごい速度で後ろに流れ去ってゆくように見えたという。建物や街路樹もちかちかと光って見え、信号も実際以上に煌々と輝いて見えた、と語っていた。
退院から数日たったいま、誠一の眼に、車窓からの風景はどのように映っているのだろう?
リハビリセンターへの送り迎えは、ふだんは静江が行っている。きょうは明希子が運転していた。誠一に話しておかなければならないことがあったからだ。辛い話だったが、自分たち親娘だけの問題ではない。花丘製作所で働く社員全員の問題なのだから。
しかし、明希子は切り出せないままに、センターに到着した。
「あ、りがと、よ」
と言って誠一がクルマから降りた。
明希子も降りて、誠一の隣により添うようにならんだ。
「……あ」
誠一が、センターの前庭のベンチにすわっている四十代半ばくらいの男性を見つけて声を出した。
「て、て、哲学者……だ」
「哲学者? あのひとが?」
「か、母さんと、そう呼んでる」
「お母さんとふたりで、あのひとのことをそう呼んでるってことね?」
「そ……そう。い、い、い、いっつもつもつも、む、難しい顔して、あすこに、す、すわってるから・よ」
「もう、ふたりして、そんなふうに勝手なあだ名をつけたりして」
誰かの付き添いできているのだろうか? 哲学者はノートパソコンを小脇に抱え、なるほどきょうも人生の重大テーマに取り組んでいるかのような悩ましげな表情でベンチに腰を下ろしていた。
誠一と明希子がベンチのまえを通りかかると、哲学者がふと気がついたように会釈した。
誠一も挨拶を返す。
すると哲学者が、自分の手に持っているものを示して、
「社会復帰で……パソコンを……」
とおぼつかなく言った。
明希子は、はっとした。哲学者は、付き添いでここにきているのではなく、自らのリハビリのために通ってきていたのだ。
「齢は……幾つ?」
と誠一がきいた。
「三……いやいや、五十……五、いや、五十……九」
と哲学者がこたえた。
五十九歳ということはないだろう、と明希子は思った。哲学者は、どう見ても四十代だ。五十九歳は誠一の齢だった。間もなく誠一は還暦を迎える。
すると、こんどは誠一が、
「おれは……四、十……七」
と言った。
それを聞いて、明希子はあらためて衝撃を受けた。病院で松尾から、失語症患者は数字の概念が失われていると聞いていたからだ。
「お、お大事に」
と哲学者が言い、
「あ、あ、ありがと。そ、そっちも……」
と誠一が言って、明希子とふたりその場を後にした。