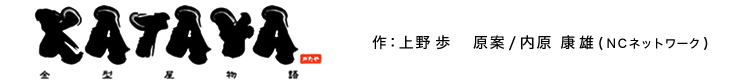

「残念ですぅ、アッコさんが会社を辞めるなんて」
理恵が言った。
理恵と明希子は、ふたりでよくくる六本木のバーで飲んでいた。
「でも、なにしろご実家の会社にかかわることですもんね」
明希子は眼のまえのカクテルグラスを眺めていた。フローズン・ダイキリ。シャーベット状のアイスが、あの日のスキー場の雪を思わせる。
「それに、アッコさんが花丘製作所にいれば、いつでも土門さんに会いに行けるし」
明希子がひとさし指を伸ばし、カウンターの隣にいる理恵のこめかみをつつくと、彼女がちろりと舌を出した。
「いいよ、ときどき遊びにきて」
「言われなくても」
「もう、ここ理恵ちゃんのオゴリだからね」
「おれのオゴリでもいいんだけどな」
振り返ると、仕立てのよさそうな白いスーツの男が立っていた。大きく開けた濃紺のシャツの襟元から金色の太いネックレスがのぞいている。南雲龍介――株式会社サウスドラゴン社長。IT業界の風雲児として日夜マスコミを賑わせている。明希子もサウスドラゴンのイベントの仕事を担当したことがあった。
「アッコちゃん、ダイ通辞めて実家の工場を継ぐんだって?」
「あら、南雲社長、ずいぶんと情報が早いんですね」
「この世でいちばん大切なものは金と情報だよ。以前から眼をつけてる魅力的な女性に関する情報となればなおさらさ」
隣で理恵が立ち上がった。
「あの、南雲社長、名刺をお渡ししてよろしいでしょうか? ダイコク通信社の佐々木理恵といいます」
南雲が無言で理恵の名刺を受け取ると一瞥もせずに上着の内ポケットに入れた。
「ダイ通さんは美人が多いんだね」
「社長のお連れの女性こそたいそうお美しいですね」
明希子は言った。
バーの入り口の方からブロンドのロングヘアーをなびかせて長身の白人女性が近づいてくると、ノースリーブの腕を南雲の腕に絡めた。
「アッコちゃん、困ったらいつでも連絡くれよ。なんだったら、お宅の会社を買ったっていいんだぜ。おれ、昔からモノづくりってやつに興味があるんだよね」
――すでにじゅうぶんに困っておりますが、あなたのところにだけは連絡するつもりはありません。
明希子はバーの奥へと消えてゆく二人の後姿を見送った。
「お金と情報か……」
と理恵がぼんやり言った。
「ねえ、理恵ちゃん。以前、あなたに“マーケティングマネージャーにとっていちばんたいせつなものはなんだと思う?”ってきいたよね」
「ええ。そしたら、アッコさんは“判断と運”だって」
「たしかにそう言った。でもね、今夜、ここでそれを訂正する。マーケティングマネージャーにとっていちばんたいせつなもの、それは判断と覚悟よ」
――いまはわたし自身がその言葉を心の片隅に留めておこう。そうして、なにかあったら取り出して眺めよう。いちど決心したら、腹を据えてとことんやる。それしかないんだ。
「お飲みものはおなじものでよろしいですか?」
明希子のまえの空いたグラスを見てバーテンダーがきいた。
「そうね、マティーニをお願い。うんとドライにして」
と明希子は言った。
「もう甘いカクテルはいらない」
EMIDAS magazine Vol.14 2007 掲載
※ この作品はフィクションであり、登場する人物、機関、団体等は、実在のものとは関係ありません