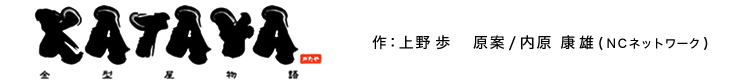

「――なにより花丘製作所とわたしは双子の姉妹のようです」
と明希子は、食堂に集合した社員全員に向かって言っていた。
まずさいしょに、明希子は、「おはようございます」と朝の挨拶をした。
「このたび十二月八日の臨時株主総会で可決され、花丘製作所の代表取締役社長に就任しました花丘明希子です」
それは社長としての自分の所信表明だった。
明希子は自分の言葉で、飾ることなく自分の気持ちをみんなに伝えようと思った。
「そう、花丘製作所は、わたしの分身なんです。会社が創立してからすこしして、わたしも生まれました。わたしはこの分身のおかげでごはんが食べられたし、学校にも通えたんです」
昨夜、バスタブに浸かりながら練習した挨拶を述べながら明希子は社員の顔を見渡した。知った顔もいる。まだ馴染みのない顔もいる。菅沼が嬉しそうにこちらを見ている。葛原はなにやら感慨深げで、涙でもこぼしそうだ。土門がなにを考えているのかは、相変わらずその表情からは読み取れない。にやにやしながら落ち着かなくからだを揺すっていた菊本が、里吉に頭をはたかれている。
「すこしだけお姉さんの分身に、父は深い愛情を注いでいました。わたしが小学校の時、父は約束したのに運動会にきてくれなかった。きっと、なにかあったのだろうと、わたしはわたしの分身に嫉妬しました」
誠一はこの場に姿を見せていなかった。「これからは、おまえの時代だ」と言って。あるいは、落合の言葉ではないが、先代社長の姿がいつまでもちらつくことで社員の気持ちが明希子に向かないことを気にしたのかもしれない。
「そうしていま、その分身はとても悪い状態にいます。わたしは、自分のたいせつな分身を失うわけにはいかないんです」
食堂に集まった社員の顔は、自分を歓迎してくれてばかりはいなかった。懐疑的な表情でこちらを見ている者、あきらかな敵意を持ってにらんでいる社員もいる。
明希子は、あらゆる表情と対峙していた。
事務室の奥にある社長室に入ると、明希子は執務机にそっと手を触れた。このあいだ誠一が触れていた机に。革張りの椅子に腰を下ろす。肘掛の付いたその椅子は、自分には大き過ぎた。
ノックの音に、「はい」と返事をする。
「おはようございます」
経理の恩田昌代が入ってきた。昌代は四十五歳で独身である。誠一や菅沼からの信頼も厚い。地元の商業高校卒業と同時に花丘製作所に入社し、以来勤続二十七年。眼鏡をかけた、もの静かで、美しいといってよい女性だが、「わたしの青春は花丘製作所に捧げた」が口癖だ。そうして、なにかの拍子に、屈託のない笑顔を浮かべた彼女の唇からこの言葉が発せられる時、周囲にいる者は彼女の来し方に思いをはせ、あいまいな表情で沈黙するしかないのだった。
昌代が、漆の盆に載せてきた湯飲みを机に置いた。
「ありがとう。でも、気にしないで。あしたからは自分でするから」
明希子は言って、せっかくなので昌代がいれてくれたお茶をひと口飲んだ。
「おいしい!」
ほんとうだった。
「恩田さんて、お茶をいれるの、とっても上手なのね。なにかコツがあるの?」
昌代が笑って、
「特別な裏業みたいなものがあるわけじゃないんですよ。そうですね、あるとしたら、飲むひとの好みに合わせた温度にいれることかしら。社長は、あまり熱くないのがお好みですよね?」
「ええ」
“社長”と呼ばれて、明希子はなんとなく居心地が悪かった。
「ずっと以前に会社にいらした時、お茶をお出ししたら、熱いのが苦手とおっしゃっていたので」
「わたし、猫舌なんだ。でも、よくおぼえているのね」
昌代はにこにこと、ただやさしげな笑みを浮かべていた。
「父は熱いお茶が好きなのよね」
「ええ。舌が焼けるほどに。それに毎朝、梅干もいっしょにお出ししていました」
「そうそ、熱いお茶に梅干」
明希子はつかの間、父の姿を思い浮かべることで先ほどからの緊張からとかれるような気がした。